迷ったらコレ!中学生の自由研究におすすめの簡単テーマ9選&使える施設5選

※公開日時点の情報です。
「自由研究って何をやればいいか分からない」
「簡単に終わるテーマが知りたい」
夏休みが近づくと、そんな悩みを抱える中学生も多いのではないでしょうか。
でも、難しく考える必要はありません。身近な材料やちょっとした発想で、理科の学びにもつながる自由研究はたくさんあります。
この記事では、中学生でも簡単にできる自由研究テーマと、アイデアのヒントが見つかる注目スポットを厳選してご紹介します。
短期間で完成できて、ほかの子とかぶりにくいテーマばかりなので、今年の夏は、自分らしく楽しく自由研究に取り組んでみましょう。
1.【身近な不思議を調べよう】中学生向け!簡単にできる自由研究

日常のなかには、「どうしてこうなるの?」と感じる小さな不思議がたくさんあります。
自由研究は、そんな疑問に目を向けて調べることで、ぐっと面白くなっていきます。
ここでは、特別な道具を使わなくても、家や近所でできる観察や記録をもとにしたテーマをご紹介。
準備もシンプルで始めやすく、理科の学びにもつながります。
夏休みの宿題に取りかかる第一歩として、自分のまわりにある自然や現象に注目してみましょう。
1.植物の成長記録 2.星の動きの観測 3.昆虫標本作り
(1)植物の成長記録|豆苗の再生栽培で成長を比較観察
身近な不思議に注目するテーマのなかで、まずおすすめしたいのが植物の成長記録です。
特に豆苗は、再生栽培ができることで知られています。
一度カットしたあとでも、根の部分を水に浸しておくだけで再び芽が伸びてくるため、成長の様子を手軽に観察できるのが大きな特長です。
毎日決まった時間に写真を撮ったり、茎の長さを測ったりすることで、成長のスピードや形の変化に気づくことができます。
条件を少し変えて、水の量や置き場所(直射日光・日陰など)による違いを比べてみるのもよいかもしれません。
結果はグラフやイラストにまとめて見せると、レポートの見栄えもよくなります。
難しい準備は必要なく、スーパーで買った豆苗がそのまま使えるので、思い立ったその日から始められるのも嬉しいポイントです。
(2)星の動きの観測|北極星を中心とした星の動きを記録しよう
夜空を見上げると、星がきれいに輝いていますが、実は時間とともにその位置が少しずつ動いていることをご存じでしょうか。
なかでも北極星はほとんど動かないため、まわりの星の動きを比べて観察するのにぴったりです。
自由研究として取り組む場合は、晴れた日の夜に同じ場所から星空を見上げ、1〜2時間ごとに空の写真を撮影するか、方位と高さをメモして記録してみましょう。
星座アプリを使えば、星の名前や位置も簡単に確認できます。
動きの変化を矢印や図でまとめれば、時間ごとの星の動きがひと目でわかる観察レポートになります。
特別な道具は不要で、夏休みの夜の静かな時間を使ってじっくり取り組める研究テーマです。
(3)昆虫標本作り|身近な昆虫で生物の分類を学ぼう
自然の中で見つけた昆虫を使って標本を作ることは、生きもののしくみや違いを知る良いきっかけになります。
身近な公園や庭、空き地などで見つけた昆虫を採集し、その種類や特徴を記録しながら標本にしていきましょう。
昆虫は「チョウ目」「コウチュウ目」など、分類ごとに体のつくりや模様が異なるため、比べてみると興味深い発見があるはずです。
捕まえた昆虫はティッシュにくるんで冷凍庫で一晩寝かせ、虫ピンや厚紙を使って形を整えると、きれいな標本が作れます。
あわせて体のつくりをスケッチしたり、生息地の違いを地図にまとめたりすると、より深みのある自由研究に仕上がるでしょう。
2.【身近なもので科学体験】中学生におすすめの簡単自由研究

「科学」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、実は台所やリビングにあるものを使って手軽に体験できる実験がたくさんあります。
普段の生活では気づきにくい現象も、やり方を少し工夫するだけで「どうしてこうなるの?」という発見につながります。
ここからは、身近な材料を使って化学変化や成分の不思議を体感できるテーマをご紹介。
すぐに始められる内容ばかりなので、夏休みの後半に取りかかっても間に合います。
驚きと学びがつまった実験に挑戦してみましょう。
1.重曹とお酢の反応実験 2.牛乳の秘密を探る 3.カフェインをとり出してみよう
(1)重曹とお酢の反応実験|台所にあるもので化学反応を観察しよう
科学の世界を身近に感じたいなら、重曹(炭酸水素ナトリウム)とお酢(酢酸)を使った発泡反応の実験がおすすめです。
重曹はベーキングパウダーとして使われることも多く、家庭にあるケースが多い材料です。コップや紙皿などの容器に重曹を入れ、そこに少しずつお酢を注ぐと泡がぶくぶくと発生しますが、これは二酸化炭素が発生している証拠となります。
この泡が出てくる様子を観察しながら、「なぜふくらむのか」「どれくらい泡が出るのか」といった点に注目してみましょう。
分量を変えて反応の強さを比べたり、容器の形によって泡の広がり方がどう変わるかを比べてみるのもよいかもしれません。
ペットボトルを使えば、風船を膨らませる実験にも応用できます。
実験の過程は写真に残し、結果は表やグラフにすると伝わりやすくなります。
短時間で結果が見えるだけでなく、安全で後片づけがラクな点も取り組みやすさのポイントです。
(2)牛乳の秘密を探る|なぜ白いのか身近な疑問を解決しよう
毎日のように飲んでいる牛乳ですが、「なぜ白いのか」と聞かれて答えられる人は意外と少ないのではないでしょうか。
実は牛乳の白さには、たんぱく質や脂肪、カルシウムなどが関係しています。
これらの成分が光を乱反射させることで、白く見えるのです。
この自由研究では、牛乳をろ紙やフィルターでこしてみたり、水や豆乳など他の液体と色の見え方を比べたりすることで、その仕組みを調べられます。
また、温めたときの変化や時間が経ったときの成分の分離も観察ポイントです。
実験中に感じた疑問や変化の様子を記録しながら、白く見える仕組みを視覚的にまとめていくと、理科的な要素をしっかり押さえたレポートに仕上がるでしょう。
(3)カフェインをとり出してみよう|緑茶からカフェインを抽出する実験
お茶やコーヒーに含まれていることで知られるカフェインは、私たちの身近にある成分のひとつです。
この実験では、緑茶の茶葉からカフェインを抽出することで、目には見えにくい成分を取り出す体験ができます。
やり方は、茶葉をお湯で煮出したあとにろ紙でこし、氷水で冷やすというシンプルなもの。
さらに、精製したカフェインをアルコールや油などに混ぜて比重の違いを観察する方法もあります。
抽出した液を乾燥させて白い結晶を観察できれば、見た目にも達成感のある結果になります。
作業中は火を使う場面があるため、必ず保護者に一言伝えてから行いましょう。
理科の授業では触れにくい成分の仕組みに、自分の手で迫ることができる探究型の研究です。
3.【家でできる簡単実験】中学生向け!物理・工学の自由研究
家の中にあるもので、物理や工学の原理に触れられる実験も、自由研究にはぴったりです。「なぜこうなるの?」という疑問をもとに、身近な素材で仕組みを試したり比べたりすることで、楽しく学ぶことができます。
大がかりな道具や難しい準備は必要ありません。
ここからは、エネルギーや力の伝わり方、空気の働きなどをテーマにした、家で取り組みやすい実験をご紹介します。
1.備長炭電池を作ってみよう 2.紙をまっすぐに落とす研究 3.保冷効果の研究
(1)備長炭電池を作ってみよう|備長炭とアルミホイルで発電実験
電池といえば買うものというイメージがありますが、実は家にある材料を使って電気を生み出すことができます。
その代表的な例が、備長炭とアルミホイルを使った手作り電池の実験です。
備長炭は電気を通しやすく、アルミホイルとの組み合わせで電位差が生まれるため、食塩水に浸すことで微弱な電流を得ることが可能になります。
豆電球を光らせたり、テスターで電圧を測定したりすることで、発電の仕組みを具体的に理解できるでしょう。
材料はすべて100円ショップや家庭にあるものでそろうため、特別な道具を用意する必要はありません。
エネルギーの仕組みを体感できる自由研究として、ぜひ試してみてください。
(2)紙をまっすぐに落とす研究|空気抵抗と落下の関係を調べよう
紙を高いところから落とすと、くるくる回ったり、左右に揺れたりしながら、ゆっくりと落ちていくことがあります。
これは「空気抵抗」の影響によるもので、紙の形や大きさによって落ち方が変わる点に着目したのが今回の研究テーマです。
コピー用紙を細長く切ったり、折りたたんだり、丸めたりして、さまざまな形に加工し、どれが一番まっすぐに、あるいは速く落ちるかを比較してみましょう。
身近な材料と道具だけで、自宅で簡単に挑戦できます。
落下の速さや動きを調べるには、ストップウォッチで時間を計ったり、動画を撮って観察したりするのが効果的です。
ただし、比較するためには条件をそろえることが大切です。
使用する紙の重さや大きさ、落とす高さなどはすべて統一しましょう。
特別な準備がいらないので、思いついたときにすぐ試せるのが魅力です。
物理の基本を体感しながら、楽しく取り組んでみてください。
(3)保冷効果の研究|缶ジュースの冷たさを保つ方法を比較
暑い夏に飲む冷たいジュースを、できるだけ長く冷たいまま保ちたいと思ったことはありませんか。
この研究では、缶ジュースの冷たさを保つには、どんな工夫が効果的なのか比較します。
冷たい缶ジュースと温度計があれば、自宅ですぐに始められる手軽な実験です。
たとえば、アルミホイルで包む、タオルを巻く、保冷バッグに入れるなど、家庭にあるもので簡単にできる工夫をいくつか試して、それぞれの方法で時間ごとの温度変化を記録していきましょう。
温度計があればより正確に測定でき、グラフにまとめると違いが見やすくなり説得力も増します。
また、結果だけでなく「なぜこの方法が効果的なのか」を考察することで、熱の伝わり方や断熱の仕組みについても理解が深まるでしょう。
生活に身近なテーマだからこそ、興味を持って取り組める物理系の自由研究としておすすめです。
4.中学生が簡単な自由研究を完成させるための3ステップ

自由研究は、やみくもに始めるよりも、流れを意識して取り組むことでスムーズに進めやすくなります。
ここでは、それぞれのステップで何を意識すればよいかを具体的に解説します。
短期間でもしっかり仕上げたい人に役立つ内容となっているので、ぜひ参考にしてください。
(1)テーマを選ぶ|興味のある分野から「なぜ?」を見つけよう
自由研究のスタートは、なんといってもテーマ選びです。
短期間で終わらせたいときほど、自分の興味に合った分野から選ぶことが成功のポイントになります。
好きな教科や趣味、ふだんの生活の中で「これってどうして?」と思ったことを出発点にしてみましょう。
たとえば、料理が好きなら食品の変化、空を見るのが好きなら天体観測など、自分らしさを活かしたテーマは取り組みやすくなります。
また、準備に時間がかかりすぎないか、実験や調査が1日で終わるかどうかも事前にチェックしておくと安心です。
気になるテーマが複数ある場合は、取り組みやすさや面白さを比べて、今の自分に合ったものをひとつに絞っていきましょう。
(2)実験の計画を立てる|仮説→実験→考察の流れを意識しよう
テーマが決まったら、すぐに実験に取りかかるのではなく、まずは進め方を整理してから始めることが重要です。
最初に「こうなるはずだ」という自分なりの仮説を立て、それを確かめるためにはどんな方法がよいかを考えてみましょう。
実験や観察の手順、必要な道具や材料をノートに書き出しておくと、準備や実施がスムーズに進みます。
また、実験中は結果だけでなく、その過程で気づいたことや予想と違った点もこまめに記録しておきましょう。
最後に「なぜこうなったのか」を自分の言葉で振り返ることで、より納得のいくまとめにつながります。
限られた時間の中でも、しっかりとした計画を立てて取り組むことで、内容の充実した自由研究に仕上がるはずです。
(3)まとめる|写真や図表で分かりやすく伝えよう
自由研究の仕上げとして重要なのが、結果や考察をわかりやすくまとめる作業です。
どんなに面白い実験をしても、内容が伝わらなければもったいないですよね。
見やすくわかりやすいレポートに仕上げるためには、写真や図表を活用するのがおすすめです。
たとえば、実験の過程や結果を写真で並べたり、観察データを折れ線グラフにしたりすると、文章だけでは伝わりにくい変化や違いが一目でわかるようになります。
また、タイトルや見出しをつけて構成を工夫することで、読み手にとって親切なレポートになります。
結果だけでなく、「やってみて感じたこと」や「次に試してみたいこと」など、自分の言葉を添えることも大切です。
仕上げのひと工夫で、見る人の印象に残る自由研究になるでしょう。
5.簡単に終わらせたい!中学生の自由研究に活用できる施設5選
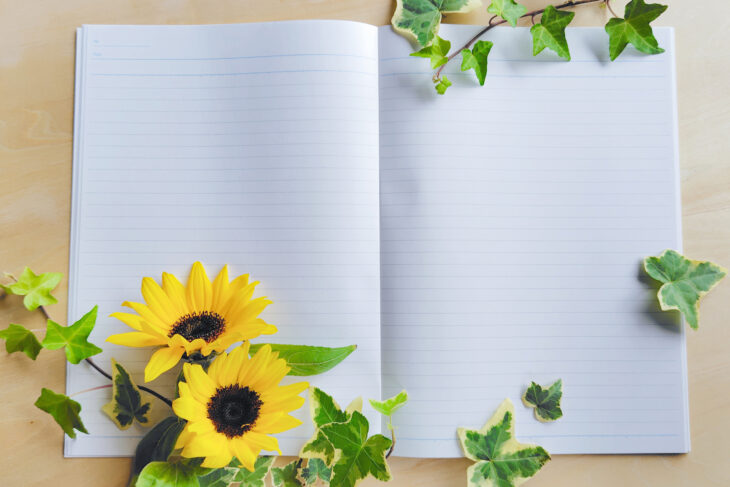
「自由研究を家で一から進めるのは大変」そう感じる人におすすめなのが、体験型の科学館や見学施設を活用する方法です。
展示やワークショップを楽しみながら学べるため、自然とテーマが決まり、レポートにまとめやすくなります。
ここからは、関東を中心に、理科の知識が深まる施設や、実際の製造工程を見学できる施設をご紹介します。
その場で得た学びをもとに、オリジナルの自由研究に仕上げてみましょう。
(1)多摩六都科学館
プラネタリウムと体験展示で宇宙科学を学ぼう
この投稿をInstagramで見る
東京都西東京市にある多摩六都科学館は、好奇心をくすぐる体験がたっぷり詰まった、自由研究のテーマ探しにぴったりの体験型科学館です。
館内にはチャレンジの部屋、からだの部屋など5つの展示室があり、力・光・音といった物理の基本原理を自分の手で体験しながら学べる展示が揃っています。
展示内容は中学生にも十分見ごたえがあり、気になった展示をもとに自分でテーマを設定しやすいのが特長です。
そして目玉は、世界最大級を誇るプラネタリウム。
夏の星座や惑星の動きがリアルに映し出され、まるで宇宙を旅しているような気分になれます。
見て・触れて・感じる体験が盛りだくさんなので、観察記録や撮影を通じて、帰宅後に自由研究としてまとめるための材料が揃うでしょう。
施設名
多摩六都科学館
住所
東京都西東京市芝久保町5-10-64
アクセス
【電車】
西武新宿線「花小金井駅」よりバスで約8分
営業時間
9:30~17:00(入館は16:00まで)
定休日
月曜日(祝日及び振替休日は開館し、翌日休館)、祝日の翌日、年末年始、機器整備の休館日あり
入場料
【入場券(展示室)】
大人:520円
小人(4歳~高校生):210円
【観覧付入館券(展示室+プラネタリウムまたは大型映像を1回)】
大人:1,040円
小人:420円
【セット券(展示室+プラネタリウムまたは大型映像を1回)】
大人:1,460
小人:530円
【上記の券にプラネタリウムまたは大型映像を1回追加】
大人:520円
小人:210円
駐車場
あり(有料)
電話番号
042-469-6100
公式HP
多摩六都科学館
(2)メッツァビレッジ
自然体験アクティビティで環境学習を実践
この投稿をInstagramで見る
メッツァビレッジは、豊かな自然と北欧スタイルを体験できる施設です。
自然に囲まれた心地よい環境で、自然観察や昆虫学習などが気軽にでき、中学生の夏休み自由研究にもおすすめです。
そんなメッツァビレッジ内では、2025年8月2日に「昆虫の標本づくり」ツアーを開催。
このツアーでは、午前中にフィールドで昆虫を採集し、午後には標本作りに挑戦できます。
さらに、8月17日には「夜のセミ観察」ツアーの開催も予定されています。
こちらは夕方に抜け殻を集め、標本として整理した後、暗くなってから実際に羽化するセミを観察するというドキドキのプログラム。
どちらのプログラムも、講師の指導のもとで採集や観察、記録までの研究の流れが体験できるため、自由研究としてそのまま使える内容になっています。講師がつき添い、「なぜこうするのか」「どう記録するか」を丁寧に教えてくれるので、研究としての質も抜群です。
参加するだけで自由研究の素材がすべて揃うので、何をテーマにすればいいか分からないと悩んでいる人にこそおすすめです。
どちらも人気プログラムなので、気になる方は早めのチェックをおすすめします。
「昆虫の標本作り」の開催日程や詳細については、こちらも合わせてご覧ください。
「夜のセミ観察」の開催日程や詳細については、こちらも合わせてご覧ください。
施設名
メッツァビレッジ
住所
埼玉県飯能市宮沢327-6
アクセス
【電車】
西武線「飯能駅」から路線バスで13分
(詳しくはこちら)
【車】
圏央道狭山日高I.Cから県道262号線経由約5.4km
圏央道青梅I.Cから県道218号線経由約11km
営業時間
平日:10:00~18:00
土日祝:10:00~19:00
※季節・イベントにより変動あり
定休日
不定休
入場料
無料
※一部有料コンテンツあり
駐車場
あり
電話番号
0570-03-1066
公式HP
メッツァビレッジ
(3)明治なるほどファクトリー
乳製品の製造工程で食品科学を学ぼう
この投稿をInstagramで見る
明治なるほどファクトリーは、牛乳・チーズ・チョコレート・ヨーグルトなど、身近な食品がどのように作られているのかを見て・聞いて・体験できる工場見学施設です。
全国に工場があり、中学生の自由研究に活かせるヒントがたくさん詰まっています。
見学では、最新の安全管理の方法や原料の選び方、栄養についても、映像や実物を通してわかりやすく学ぶことができます。
さらに、カカオ豆や乳酸菌の香りや見た目、成分を実際に観察できるのも魅力のひとつ。
たとえば、大阪・高槻市の工場では、見学通路から動く機械の様子を間近で観察でき、チョコレートの試食体験も楽しめます。
参加するだけで観察から体験、記録と自由研究の素材が一度に集められるため、あとは帰宅後にまとめるだけ。
工場で観察した内容をもとに「原料から製品へどう変わるのか」「どうやって安全を守っているのか」などを研究テーマにして、レポート化するのも面白いでしょう。
施設名
明治なるほどファクトリー
住所
大阪府高槻市朝日町1-10
アクセス
【電車】
JR京都線「摂津富田駅」より約15分
【車】
名神高速「茨木」IC より約15分
営業時間
月曜日~金曜日 1日2回(9:30~(10:00~)、13:30~)
※開始時間は要相談
定休日
要問い合わせ
入場料
無料
駐車場
あり(8台)
※公共交通機関の利用を推奨
電話番号
072-685-5031
公式HP
明治なるほどファクトリー
(4)がすてなーに
ガスの科学と環境エネルギーを楽しく学ぼう
この投稿をInstagramで見る
がすてなーには、私たちの暮らしを支えるエネルギーや、これからの社会・環境問題を楽しく学べる体験型の施設です。
館内は「エネルギー」「エナジースタジオ」など7つのゾーンに分かれ、液体窒素を使った実験やARを活用したデジタル展示、地球温暖化やSDGsにつながるコーナーが充実。
専門のコミュニケーターがそばで丁寧に解説してくれるので、「なぜ?」をどんどん追求できます。
2025年の夏休み期間中には、ポケットプログラムや料理教室といった体験型イベントが開催されるのも特徴です。
ガスの安全装置やエネルギーの仕組みについて楽しみながらわかりやすく学べるため、その場で得た疑問や発見をもとに調べれば、自由研究のレポートの土台が完成するはず。
施設での体験を通じて、レポートに使えるエピソードや記録がたくさん残るでしょう。
エネルギーのしくみや環境問題に興味がある人は、夏休みにぜひ訪れてみてください。
施設名
がすてなーに
住所
東京都江東区豊洲6-1-1
アクセス
【電車】
東京メトロ有楽町線「豊洲駅」より徒歩6分
【車】
首都高速晴海線「豊洲」ICより約5分
営業時間
9:30~17:00(入館は16:30まで)
定休日
月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始、施設点検日
入場料
無料
駐車場
あり
電話番号
03-3534-1111
公式HP
がすてなーに
(5)つくばエキスポセンター
最新科学技術の展示で未来の研究を体感
この投稿をInstagramで見る
つくばエキスポセンターは、茨城県つくば市にある「国際科学技術博覧会」の記念施設を引き継いだ体験型科学館です。
館内の展示は、宇宙・海洋・生命科学など多彩な分野をカバーし、1階・2階展示室に加え、屋外には本物そっくりのH‑IIロケット実物大模型がそびえ立つなど、見て触れて学べる仕掛けが満載です。
学びと記録がセットで揃うので、自宅での自由研究のレポート化もスムーズに進められるでしょう。
そして、この夏注目のイベントは2025年7月12日より開催予定の「エキスポ昆虫ランドへようこそ-昆虫を感じてみよう!-」。
この企画展は、私たちの身の回りにたくさんいる昆虫が持つ「すごいチカラ」を、体験を通して感じられるイベントです。
小さな体でも、飛んだり鳴いたり、時には戦ったりする昆虫たちの驚きのパワーに触れることができるでしょう。
好奇心を刺激するだけでなく、研究の材料としても充実しているのが嬉しいポイントです。
夏休みは、つくばエキスポセンターで科学者気分を味わいながら、自由研究のテーマを完成させてみませんか。
施設名
つくばエキスポセンター
住所
茨城県つくば市吾妻2‐9
アクセス
【電車】
首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス「つくば駅」より徒歩5分
【電車・バス】
JR常磐線「ひたち野うしく駅」または「荒川沖駅」よりバスでつくばセンターバス停下車徒歩5分
【車】
圏央道つくば中央I.Cより約10分
常磐自動車道桜土浦I.Cより約15分
営業時間
9:50~17:00
定休日
月曜日、年末年始
※臨時休館日あり
入場料
【入館券】
おとな(18歳以上):500円
こども(4歳~高校生):250円
【プラネタリウム券】
おとな:500円
こども:250円
駐車場
あり
電話番号
029‐858‐1100
公式HP
つくばエキスポセンター
3.まとめ
自由研究は「簡単に終わらせたい」と思っていても、テーマ選びに迷ったり、どう進めればよいかわからなくなったりしがちです。
今回ご紹介したテーマは、どれも身近な材料や家にある道具で手軽に取り組めるものばかり。
自分の興味に合わせて選ぶことで、短期間でもしっかり学びにつなげることができます。
施設を活用すれば、楽しみながらまとめやすいテーマを見つけることも可能です。
大切なのは、難しく考えすぎず、「これ面白そう」と思えるものにチャレンジしてみること。
身のまわりの疑問を深掘りしたり、実際に体験したことを自分の言葉でまとめたりすれば、自分らしい自由研究がきっと完成するでしょう。
ぜひ夏休みの思い出に残る研究に取り組んでみてください。




















